心配性の人に振り回されないために ― 「助けたい」と「巻き込まれる」の境界線
今回は、身近にいる心配性の人ととのかかわり方について、
取り上げたいと思います。
ことあるたびに、ネガティブに考えたり、
「大丈夫?」と常に不安を口にする。
特に、自分自身が前を向いている時に、
変に足が引っ張られる気がして、
気分が重くなってしまうときもありますよね。
特に心配性の人が親の場合は、
愛情があるから心配しているんだよって、
人は言うかもしれませんが、
身近な人ほど、影響を受けてしまいますよね。
今回は、心配性の人とどう距離を取り、
どんな姿勢で関わればいいのかを書いていきたいと思います。
目次
心配性の人は「安心」を外側に求める
心配性の人は、「何か起きたらどうしよう」と、
常に未来に、そして良くない面に意識が向いています。
そして、その不安を少しでも軽くしようとして、
周囲に確認したり、助けを求めたりします。
例えば、「病気になって手術することになった。」
この事実に、即答「無事手術を終えて、元気に回復するように」
だけに留まれないのが心配性。
手術は成功するかな?
大丈夫かな?先生は?
とにかく、まだ何も起こっていない状態から、
「起きてほしくない良くないこと」へ意識を向けてしまうんです。
そして大丈夫だったという確認を過度に聞きたがったり、
確認したり。自分はどうにもできないのに、心配からイライラしたり。
これでは、「私の心配をどうにか埋めて!」と外側に求めている状態です。
「助ける」と「巻き込まれる」は紙一重
心配性の人が不安を口にするとき、
それはあまり心地いいものではありません。
基本的に、心配性の人から出てくるものって、
ネガティブな発言が多いので、
周りをどっしり重くさせる雰囲気があります。
そんな心配症の人に対して、
「大丈夫だよ」
「こうなるよ」などと答えたくなることもあるでしょう。
ただ、ネガティブに対して、そのたびに私たちが不安を「処理してあげる」と、
次第に、自分自身が疲れていきます。
相手の不安に巻き込まれて疲弊している時は、
それは境界線が曖昧になっているサイン。
相手が不安を感じることも、心配することも、
“その人自身の課題”です。
なんとかしようとすることで、
相手自身が自分の中で安心を作る練習の機会を失う必要もないし、
私たちが心配を引き取る必要はありません。
安心を取り戻す責任は、本人にある
もし、相手の不安を聞くたびに自分がモヤモヤするなら、
「私は今、何を背負おうとしているんだろう?」
と一度立ち止まってみてください。
こちらは「安心させる係」ではありません。
相手の感情を受け止めることと、解決してあげることは別の話です。
「不安なんだね」「そう感じているんだね」と受け止めても、
必要以上に抱え込まない。
その線を引けるかどうかが、関係を健全に保つ鍵です。
心配性の人に振り回されないためには、
「どこまでが自分の責任で、どこからが相手の領域か」を明確にすること。
相手の不安をなんとかしようとしすぎず、
自分の安心を守ることも、同じくらい大切です。
あなたは最近、誰かの「不安」を自分の中にまで持ち込んでいませんか?
その不安は、本当にあなたが背負うべきものでしょうか。
それとも、相手の安心を引き受けようとしているだけかもしれません。
一度、境界線を引き直して、「ここから先は、相手の課題」と区切りましょう。
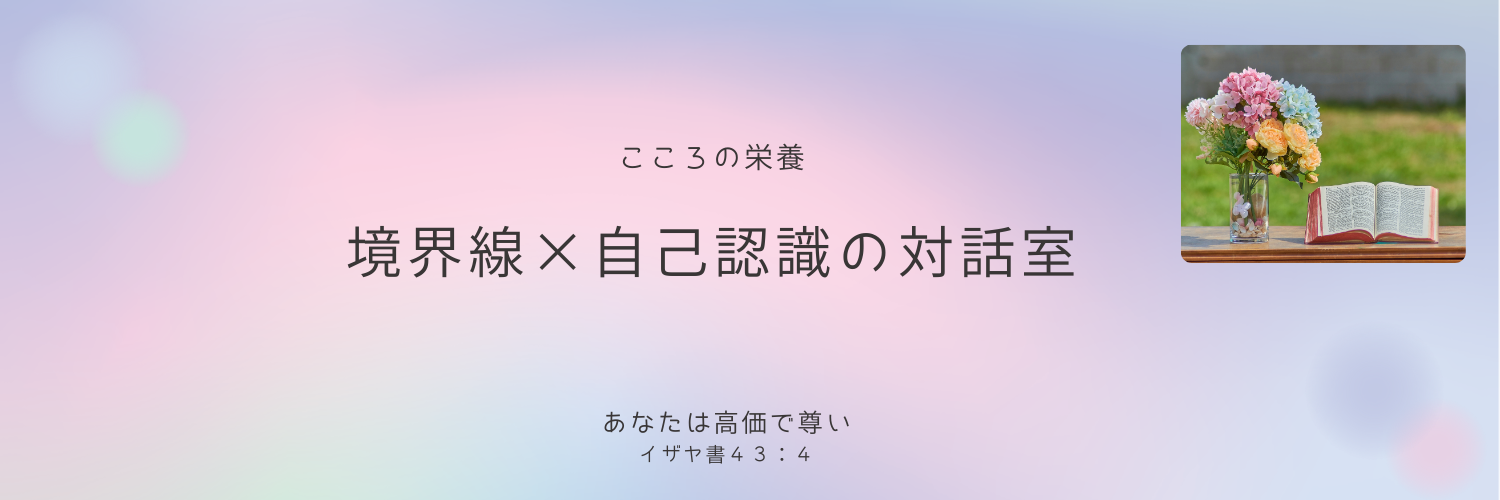
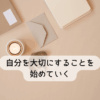
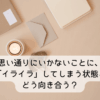
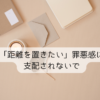
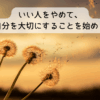
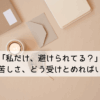

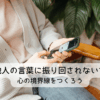
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません