「親の介護は子どもの義務?」― 親子関係に適切な境界線を引く
今回は「親の介護と境界線」について取り上げたいと思います。
まず最初にお伝えしたいこと。それは、
子どもには、親を介護する義務はないということです。
より正確に言えば、「義務感から介護を始めないでほしい」
ということを伝えたいです。
その理由を3つの視点からお話しします。
目次
➀ 介護はプロの世界
介護は専門職の領域です。
病気になったら医者にかかるように、
介護が必要になったら専門機関や福祉サービスを頼る。
これが健全な境界線です。
親に悪性腫瘍が見つかったからといって、
子どもが責任を感じて自分で手術をするなんてありえませんよね。
同じように、介護が必要になったからといって、
「子どもがすべて担う」のは無理が生じます。
それでも現実には、
-
「身の回りのことなら助けられるのでは?」(できそう)
-
「子どもだから親の面倒を見るのが当たり前では?」(やるべき)
こうした思いが境界線を引くのを難しくさせます。
境界線を持つとは、この「できそう」と「やるべき」に対して、
自分がどこまで関われる人間なのかをはっきりさせることです。
➁ 結婚しているなら、第一優先は配偶者と子ども
もしあなたが結婚して、家庭を持っているなら、
優先すべきは実家ではなく、配偶者と子どもです。
「できる範囲で親を助けたい」という気持ちは素晴らしいですが、
親の介護に手いっぱいになり、
大事な家族を観察できなくなることは大きな危険信号です。
-
親のことに気を取られ、子どもの深刻な問題に気づかなかった。
-
親の世話で疲れ、夫婦間の孤立に気づかなかった。
これはすべて「赤信号」です。
両立・バランスという言葉は簡単ですが、
本当に大切な人を優先できているか。そのための境界線を引けているか。
ここを問い直す必要があります。
➂ 手放すことで生まれるメリット
最後は、別の視点から。
子供が介護を担うことが、本当に親にとってメリットになるのかということです。
あなたには家庭や仕事があり、時間も体力も限られています。
その中で「子どもだから」と主導することが、
必ずしも親にとって最良とは限りません。
たとえ親が「子どもに世話してほしい」と望んでも、
それを理由に子どもがすべて引き受ける必要はありません。
親自身も介護に突入する人生ステージは当然、初めての経験で、
不安から「身近な人に任せたい」と思うのは自然なことです。
しかし、本当に長期的に見て親にとって良いのは、
親本人の感情や希望がすべて正解なわけではありません。
適切な専門家に関わってもらう方がずっと効果的なことだって
多々あります。
だからこそ、子供の立場である自分の限界を認めて、
「できないことを手放す」ことは、結果的に親のメリットになることが多いのです。
~~~
今回は、
-
介護はプロの世界であること
-
家族の第一優先は配偶者と子どもであること
-
手放すことが親のメリットになること
の3つの視点から取り上げました。
境界線を引くことは、決して「冷たい拒絶」ではありません。
むしろ、本当の意味で相手を尊重し、大切な人たちを守ることにつながります。
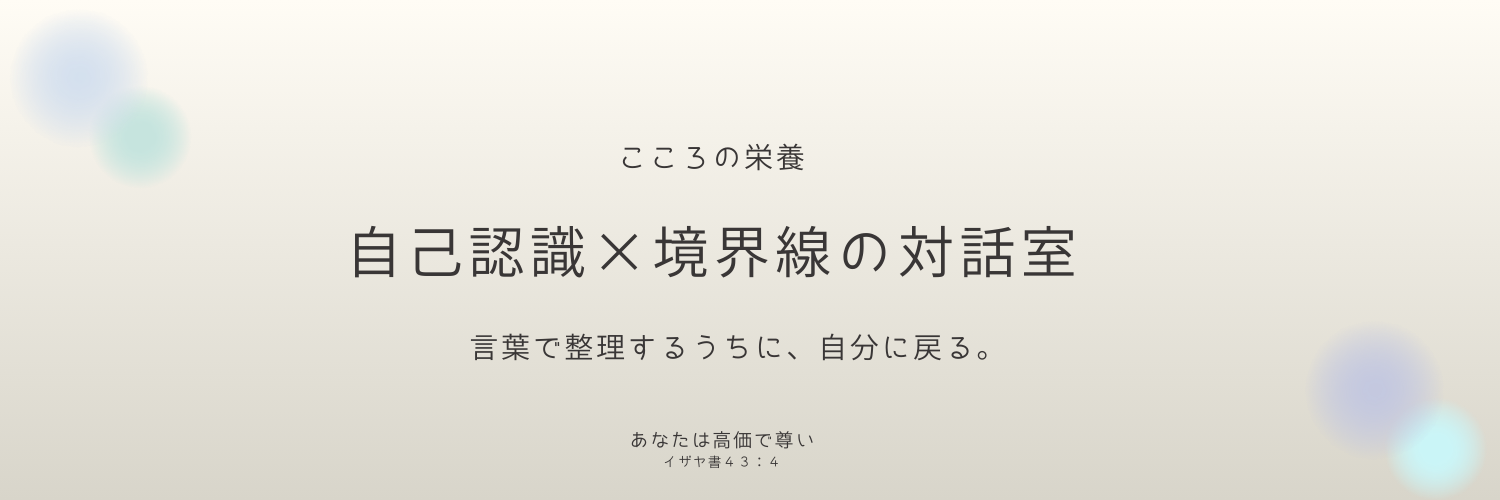
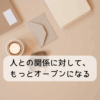
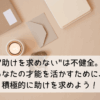
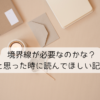
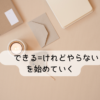
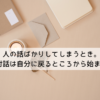


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません