「自分に厳しい」をやめるには?自分に厳しいところを緩めていく3つのメリット
私自身、以前に自分で自分に厳しいところがあるなととことん自覚した時、
「自分に厳しい」は全く持って自分の味方にならないので、手放す決断をしました。
でも、そもそも自分に厳しいって、自分で認めるまで、すごく時間がかかりました(涙)。
今なぜこんなにも時間がかかったのかと思うと、
もう一人の内なる自分が「何言ってるんだよ!」って、更に厳しいことを言ってくるんですね。
本当に、典型的な、自分に厳しい人ですね。
クリティカル・ペアレントと言って、批判的な親が自分を支配する傾向が強く出ていると、
こういう「厳しさ」が出てきます。
興味のある方は、「Critical Parent」とか、「エゴグラム」とか「交流分析」とかで、調べてみてください。
【心理学】交流分析ー人生態度「私もあなたもOK」自己肯定・他者肯定
「自分への厳しさ」というのは、決してネガティブなものだけではないです。
時に成長の起爆剤とする厳しさは健全です。
自分を過剰に責めたりとか、自分を傷つけたりする厳しさは手放す必要があります。
ただ、自分に厳しいところをやめたいと思って、
「自分に厳しいところやめていく!」と考えてしまうと、
「厳しいか厳しくないか」という0か1かという考え方になってしまいます。
それもまた、自分に厳しいので、「自分に厳しいところを緩めていく」というくらいに考える方がいいですね。
今回は、自分に厳しいところを緩めていくメリットについて書いていきます。
ぐっと握っていた力をふっと緩められるといいです。
目次
メリット1:他人に対して、もっと寛容になれる
自分に厳しいと、間違いとか、失敗とか、うまくいかなかったときに、
すぐに「ダメだ!」というレッドフラグを掲げてしまいます。
自分を裁くんですね。
誰にも何も言われていなくても、自分がちゃんと「ダメ!」「罰!」と言うんです。
すごく厳しいですね。
自分に対して、厳しいことに慣れているから、ついつい他人の失敗や間違いについても、
表立っては何も言わなかったとしても、心の中で裁いてしまうことがあるんです。
なぜなら、自分が自分で、自分を裁くということをいつもやっているからです。
だから、失敗や間違いにはすぐに反応してしまうんです。
すると、表面的には、大人の対応をしていても、心の中では、
「何、あの人!」とか、「あの人の行動はない!」とか、
人に対して否定的になってしまうんです。
【Are you Judgy?/あなたはジャッジ―な人ですか?】 すぐに批判する人、ジャッジする人
他人に対して否定的な感情を抱くのは、こころの栄養にはならないですね。
むしろ、他人の失敗なのに、自分が失敗してしまったのと同じくらい、
否定的な感情を抱いて、心は濁ってしまいます。
でも、自分に厳しいのを緩めて、自分が失敗したとき、うまくいかなかったときに、
「そういうこともあるよ。」と受け入れてあげるなら、他人にも、どんどん優しくなれたり、赦しやすくなります。
自分に厳しくするのを緩めると、他人にも優しくなれ、
人間関係も、余計な悩み事が減っていきます。すごく一石二鳥です。
メリット2:完璧よりも、成長を大切にできる
1日にできることってすごく限られています。
今日1日、一生懸命に生きて、昨日よりも成長を感じられたら、すごく人生が豊かになっていきます。
ここでの「成長」の意味は、昨日より少し、優しくなれたとか、
昨日より少し、自分を受け入れられたとか、そういう、こころの成長です。
自分に厳しい状態だと、常に自分を裁いていて、緊張感があって、
何だか常にゼイゼイしているような、ギスギスした感覚があります。
でも、自分に厳しいところを緩めていくなら、緊張が解けて、
深呼吸ができて、もっと落ち着いて過ごすことができます。
常に100点を目指すような毎日は、窮屈で息がつまります。
いつも自分をムチでたたくような厳しさでは、疲れてしまいます。
人生は仕事じゃないし、人生は営業成績じゃないんですね。
結果より、プロセス。
一瞬一瞬の時を味わい、心豊かになっていく成長を大切にできるようになると、
人生の豊かさがどんどん増し加えられていきます。
メリット3:自分の人生のことが好きになってくる
自分に厳しいことを緩めていくと、自分のことが好きになってくるんです。
毎日、怒られているよりも、怒られない方がいいですよね。
アドラー心理学「嫌われる勇気」シリーズ④ー「自分のことが嫌い」の思いとどう向き合う!?
自分の毎日の人生の中で、「毎日、怒ってくる人(自分)」が静かになってくれたんです。
これって、すごいことだと思いませんか?
誰でもいいので、いつもガミガミいってくる○○さんを思い浮かべてみてください。
その○○さんが、ガミガミ言わず、静かになったんです。
もし、その人が職場にいる人なら、仕事中の気分も上がるだろうし、
もし、その人が家族の人なら、家で過ごす気持ちも、随分と落ち着いてくると思います。
身近な人であればあるほど、共に時間を過ごす人であればあるほど、インパクトは大きいです。
まさに、自分に厳しいところを緩めるというのは、
自分に対して、厳しいことを言ったり、裁いたりしてくる自分自身が、
静かになってくれるっていうことなんですね。インパクト絶大です。
自分の人生では、主人公はいつも自分です。
自分は自分にしかなれません。当たり前のことです。
その自分が自分に対して、怒ってこなくなる。それどころか、優しくなってくる。
そしたら、怒ってばかりの時よりも、楽しくなってきます。
楽しくなってきたら、どんどん自分が好きになってきますよ。
***
「自分に厳しい」を緩めることにはメリットが沢山です☆彡



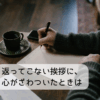



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません