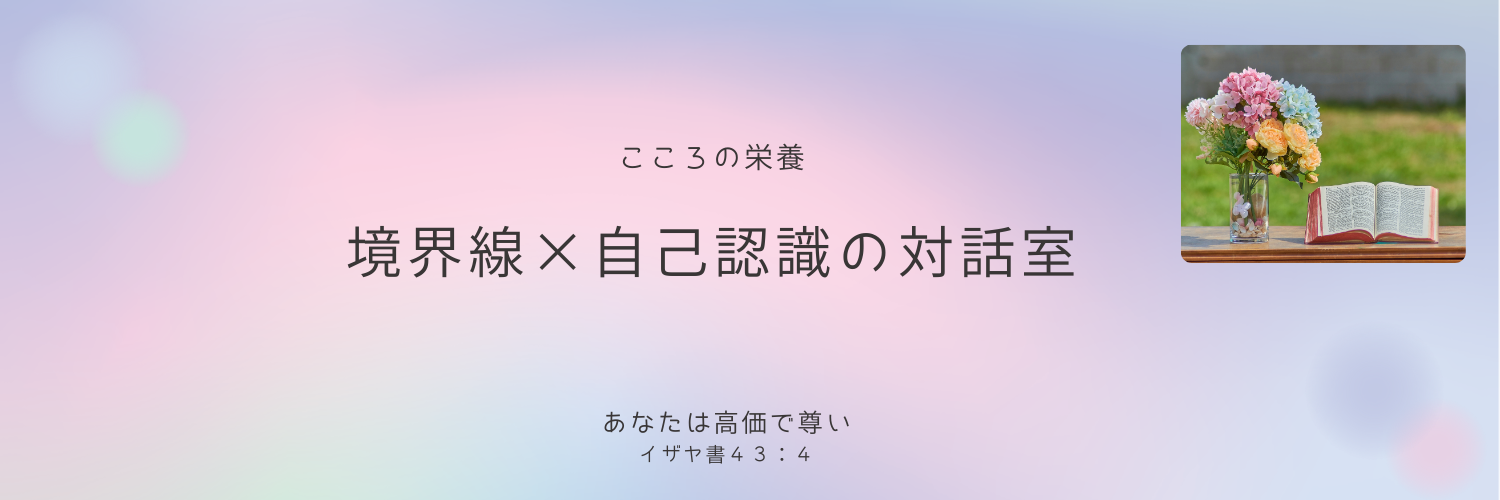「なまけもの」の完璧主義!?考えすぎて動けなくなる理由

今回は、ちょっと刺激があるテーマを取り上げます。
「完璧主義って、実は“なまけもの”の種類があるんです」という話です。
完璧主義という言葉は、真面目で努力家で、ストイックな姿勢にも聞こえますよね。
けれど、実はその裏側で“心に嘘をついている”ことがよくあります。
例えば、上司が帰り際にさらっと、
「今月の売上目標、達成に向けて頑張りましょう」と言ったとします。
完璧主義で真面目な人は、ここから頭の中でこうなりがちです。
「え、どうやって?どこから?」
「何から始めればいい?」
「自分に言った?私のこと?」
「できなかったらどうしよう…」
色々な???がどんどん湧いてきて、
気づけばひとりで過剰にプレッシャーを背負ってしまう。
そして、考えすぎて疲れてしまったり、動けなくなったりするんです。
実は「なまけもの」的構造になっている理由ここが今回のテーマです。
完璧主義の人で、実は、
今やれ ...
「調子が良くない日」への向き合い方 ―深刻にならず“波”として受け止める
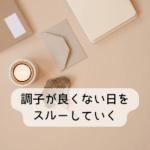
日常の中で、
「あれ、なんか今日調子よくないな」
「家族の誰かがイライラしているな」
「職場の人の雰囲気がいつもと違うな」
そんな場面に遭遇することは、誰にでもあります。
自分のことでも、他人のことでも、
「調子がいい日ばかりじゃない」のは自然なことです。
人間は感情的な生き物なので、良い時もあれば悪い時もある。
向上心がある人ほど、「毎日ちゃんと頑張りたい」という気持ちが強いので、
調子が落ちると余計に気になります。
でも、まず一番に思い出してほしいことがあります。
調子が悪い日は“波”であって、ずっと続くものではない。
だから大げさに反応しなくて大丈夫。
調子が良くない時、感情的に不安定な時、
こんな風に考えてしまっていませんか?
なんでこんなにイライラしてるんだろう?
どうしてやる気が出ないんだろう?
いつまで続くの?
でも、こうやって深刻に考えすぎるほど ...
真面目すぎてしんどい!?をやめる― 完璧主義・思い込みをほぐしていくために
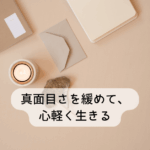
相談してくださっている方と話している時に、
「自分は真面目すぎてしまうんです」という言葉が出てきて、
その瞬間、あ、私もすごく同じだなと思いました。
私もよく「真面目」「几帳面」と言われてきました。
特に20代の頃、職場でよく言われていました。
でも、自分では全然そんな意識がなかったんですよね。
相談者の方は「真面目すぎる」という自覚があるので、
そこは私と少し違うところ。
私は、人から「真面目すぎ」と言われ、
「え、私って真面目すぎるの……?」と気づいたタイプです。
なぜ自覚がなかったかというと、
私は基本、いろんなことを“早く進めたい”タイプで、
衝動的に行動してしまうことも多いんです。
思いついたらすぐ動くし、小中学生の頃、母親から、
「行き当たりばったり」「準備不足」「雑」と言われたことも。
そんな言葉も心に残ってか、
「私は真面目」なんて思う余地が ...
人の態度を深読みして疲れる人へ ― 取り込まない習慣と境界線の整え方
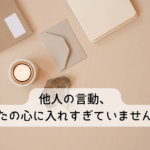
他人の言動にすぐ反応してしまう。
深読みして疲れてしまう。不機嫌に振り回される。
そんな自分にそろそろしんどさを感じていませんか?
今回は、そんなテーマに対して、書いていきます。
~~
他人に何か心無いことを言われても、
変な態度をとられても、
自分自身で深く自分の中に取り入れないこと。
これってとっても大切なことです。
境界線を持つことは、
他人は他人。自分は自分。
他人の感情、他人の行動は、あくまで他人のもの。
ここに明確な線を持つこと。
境界線が曖昧だと、
他人がこのような行動や態度をしたのは、
「自分の何かがいけないからだ」とか思ったりするんです。
でも、こういう考えをしている限り、心重苦しく、
他人に振り回されてしまいます。
よく考えたら、おかしなこと。
他人って一言で言っても、色々な人がいます。
家族や友人はもちろんの事、職場の人や、近所の人、
お店や病院の人など ...
もっと心穏やかに生きたいのに・・・イライラや焦りが続くときに見直したいこと
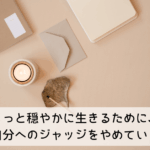
今回は、「もっと日常の中に平安を取り戻したい」
「心の落ち着きを取り戻したい」「もっと穏やかでいたい」
そんな気持ちを持っている人に向けて書いていきます。
こうした穏やかさや落ち着きを望んでいるということは、
今の現実に少し焦りがあったり、イライラしやすかったり、
待つことが難しかったり、ちょっとしたことで反応してしまったり。
という現状があるかもしれません。
まず大切なのは、
自分がどんなことを考え、何に反応し、
どんな出来事が自分を感情的・衝動的にさせているのかを把握すること。
つまり、「今の自分はどういう人間になっているのか?」を、
ジャッジせずにちゃんと見ることです。
ここでのポイントは「ジャッジしない」ということ。
自分を観察しようとすると、つい、
「だから自分はダメなんだ」「こういう過去があるから仕方ない」と、
自分を責めたり、正当化したりしてしま ...
心軽く生きていくには、私には何が必要ですか?
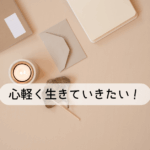
今回は、頂いたメッセージに回答します。
いろいろと読ませて頂いています。
日々、家族や友人達といろいろな事があり疲れています。
常に、イライラしたりジャッジしたり。。
何かが起こる度に、引っかかり前に進めません。人を、信じられず敵だと感じます。
心軽く生きて行くには、私には何が必要ですか?
何が必要かということですが、
「家族や友人たちと色々なことがあるから、○○」をやめることだと思います。
(○○に入るのは、できないとか疲れるとか、進まないとかそのような否定的な気持ち)
家族や友人たちは自分以外の人間ですから、もちろん色々ありますよね。
けれど、そこに振り回され続けていたら、いつまでも自分が整いません。
周りには常に誰かしら人はいるもの。
もちろん、完全に孤独になることが、自分を整え始められることでもないんです。
色々ある家族や友人たちとの中で、自分を整えていかないといけない。
だから、「家族や友人たちと色々なことがあるから、○○」をやめること ...
考えすぎて苦しいあなたへ ― 「考える」と「悩む」の違いを知るとラクになる
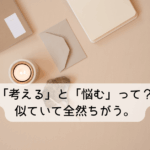
「考えすぎてしまって、いつも頭が疲れる」
「悩み始めると、ずっと同じことをぐるぐる考えてしまう」
そんなふうに感じることはありませんか?
今回は、「考える」と「悩む」の違い、
そして思考のループから抜け出すためのヒントについて書いていきます。
まず、「考える」と「悩む」は似ているようで、全く違うもの。
「考える」は、目的に向かって現実的な行動を導き出すプロセス。
一方で「悩む」は、同じ思考を何度も繰り返して、結論が出ない状態です。
たとえば、「転職した方がいいかな?」という問いを持ったとき、
・必要なスキルを調べる
・求人を見てみる
・話を聞きに行ってみる
などの行動につながるのは“考える”。
一方で、
「失敗したらどうしよう」
「でも今のままも嫌だ」と
頭の中で何度も同じ言葉を繰り返して動けなくなっているのは“悩む”。
“考える”が現実を動かすのに対して、
“悩む”は ...
「あの人のせい」でイライラ? ― 自分の充実度を取り戻すチャンス
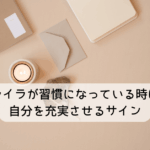
今回は、イライラしている状態とどのようにして向き合うか、
について書いていきたいと思います。
イライラしている状態というのは、自分が充実していないときに起こるサインです。
この原則を覚えておくだけで、物事への対処がぐっとスムーズになります。
「イライラする」というのは、人に対してだったり、
自分に対してだったり、さまざまなパターンがあります。
けれど、自分が満たされていて、やるべきことをきちんとやっていて、
心が充実しているときは、他人や感情に振り回されることが少なくなるんですね。
イライラしているときの対処法には大きく分けて2つあります。
ひとつは「他人を変えようとすること」。
もうひとつは「自分を変えること」です。
たとえば、イライラの原因が夫や義母、あるいは自分の母親だったとき。
多くの場合、「あの人がもっとこうしてくれたら」
「あんな態度を取らなければ ...
「人との付き合いに条件はいらない」― 自分を大切にする関係の選び方
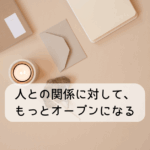
こんにちは。
今回は、人間関係全般について、取り上げたいなと思います。
まず最初に伝えたいことは――
自分に親切にしてくれる人、
よくしてくれる人、愛情を示してくれる人、気にかけてくれる人を、
本当に大切にしていますか?ということです。
世の中には、思っている以上に「良い人」「親切な人」がたくさんいます。
けれども私たちは、人間関係においてついこんな間違いをしがちです。
「この人は親だから付き合う」
「この人はいとこだから付き合う」
「同僚だから」「同級生だから」「近所だから」…
つまり、“自分との関係性”を基準にして、
付き合うかどうかを決めてしまう癖 ...
「どうしてこうなった?」ばかり考えて、疲れてない?
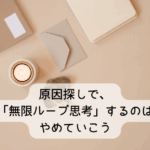
原因探しで、疲れていませんか?
たとえば、
「私って、なんでこんなふうにできないんだろう?」
「どうして、いつもこう考えてしまうんだろう?」
…そんなふうに、自分を責めること。
これって実は“期待”があるからなんです。
こうできるべき。
こう考えるべき。
そんな「自分に対する期待」を、無意識に持っています。
そして、自分でその期待をつくっておきながら、
自分で応えられずに、苦しんでしまうんです。
じゃあ、どうしたらいいのか?
「その期待、とんかちで叩いて壊しちゃいましょう。」
…なんて言うと、ちょっと極端に聞こえるかもしれませんね。
でも、本当に大事な問いはこれです。
「思い悩む原因になっている“期待”って、本当に持つ価値があるの?」
とはいえ、なかなか手放せない。なぜかというと、
「今は無理だけど、いつかは期待に応えられ ...