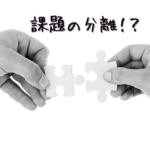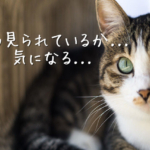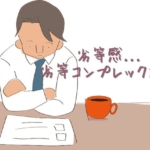共依存の家族問題にアドラー心理学を推奨する理由
今回は、アドラー心理学について取り上げます。
私は、カウンセリング手法として、特定の心理療法をサポートしているわけではありませんが、家族問題については、アドラーの考え方をおすすめしています。今回は、その理由について書いていきます。
1、課題に分離について扱っているから家族問題というのは、多くの場合、「あまりにも密接した」関係の中で生じてしまいます。友人関係や仕事の悩みとは少し種類が違って、お互いが、いい意味でも悪い意味でも「あまりにも親密」になりすぎた為に起きてしまった問題が多いです。
「親密さ」は家族関係には確かに必要なものであるけれど、同時にこの「親密さ」ゆえに、本来は相手の領域であるにも関わらず、土足でずたずた入り込んでしまうようなことがあります。相手の問題であることも自分の問題かのようにして、次第に癒着し始め、大きな問題につながってしまうのです。
家族問題のテーマのカウンセリングは、様々なものがあります。親からひどい悪口を言われた、配偶者の浮気、離婚、依存症、DV、うつ、引きこもり、ギャンブルなど様々です。ただ、課題は様々で ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」自己中心性(10)
今回は、自己中心性について取り上げます。
アドラーの言うもう一つの「自己中心性」自己中心的な人といえば、どんな人を思い浮かべますか?自分勝手な人、自分本位な人、自分の思い通りにするために、他人を困らせたり、迷惑をかける人をイメージするかもしれません。
こういう人は確かに自己中心な人ですよね。世界がまるで自分中心にすべて回っているかのように振舞います。
逆に、自己を無にして、家族のために、誰かのために身を粉にして働いたり、息子や娘のために、何から何まで尽くす人もいます。
ただ、このような他者への貢献の場合、もし、必死に頑張った人たちが、周りの家族から、何も感謝されなかったり、むしろありがた迷惑のように扱われたら、どのような気持ちになるでしょうか。
自分がやっていたことは、間違っていたのだなと素直に認められたらよいですが、心の片隅でどこか「こんなにやったのに」という不平不満が出てくる可能性が大いにあります。
そうなると、自分がやってきたことが全て否定されたような気持ちになって、大きく落ち込んだり、虚しくなってしま ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」共同体感覚(9)
今回は、アドラー心理学の中にある「共同体感覚」について取り上げます。
アドラーの言う「共同体感覚」とは何か?共同体感覚とは、アドラー心理学の中でもとても大切な考え方です。
でも、同時にこれまでの課題の分離や、幸せになる為の変化を理解して実践しないと、単独ではなかなか理解し難く、頭では分かっても、実際に取り組むのはすごく難しく感じてしまいます。
アドラーは、悩みのほとんどは、対人関係といいましたが、対人関係の理想像、まさにゴールがこの共同体感覚です。
共同体感覚は、英語でsocial interestと言い、「社会への関心」という意味です。人は1人では社会を構成することが出来ず、2人以上、つまり「私とあなた」の存在で社会になります。
難しく考えずに、家族とか、会社とか、友人とか、そういう関係をイメージしてみて下さい。共同体感覚は、まさにこのような関係で、他者を完全に「仲間」と見なします。
例えば、家族連れがチケットを買おうとディズニーランドのチケット売り場で並んでいたとします。途中から、お父さんだけが並び始め、 ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」全体論(8)
今回は、アドラー心理学「全体論」について、取り上げます。
心と身体は切っても切り離せないアドラー心理学は別名「個人心理学」とも呼ばれています。個人心理学は、individual psychologyと訳され、このindividualという単語は「(これ以上)分割できない」が語源になっているそうです。
個人とは、これ以上、分けられない最小単位であることー1人がこれ以上分割できないものであることは、考えてみれば、当たり前です。私たち人間は、自分の手も足も髪の毛も、自分に所属するものとして扱います。
アドラー心理学では、二元論的価値観に反対しています。例えば、精神と身体。もしくは理性と感情。そして意識と無意識などについてです。もちろん、それぞれは別個のものとして存在していますが、「自分の精神(心)が、こうするから、身体がこうなった」というように、あたかも精神が自分のものでありながら、他の誰かのような言い方、扱い方をすることを否定しています。
よく考えれば、私の手のせいで、足のせいで、髪の毛のせいで、こうなった・・・というのはおかしなことで ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」課題の分離2(7)
今回は、アドラー心理学「嫌われる勇気」課題の分離1(7)の続きです。
他人への過度な気遣いによって、課題の分離ができない!?アドラーは悩みのほとんどは対人関係であり、課題の分離ができていないことで問題が生じると言いますが、これが本当に難しいのは、たとえ、自分ができたとしても、「他の人は課題の分離をしてこない、できない」と心のどこかで思っていることです。
たとえば、私は、課題の分離をするけれど、「あなたは私がこうすることで、傷つくよね」とか、「私のこの行動、理解しないよね」と、どこか、相手は課題の分離ができないのではないかと思ってしまいます。
そうすると、相手がどう考えるかが気になって仕方ないので、結局自分もやっぱり課題の分離をするのをやめて、相手に合わせてしまうんです。
当然、いつまでも課題の分離が進まないので、いつまで経っても、踏み込む必要のない他人のことで悩んでしまうという循環が止まらなくなります。
特に日本人は遠慮の文化もあり、目立つことに対して消極的です。だから、理屈で「課題の分離」を理解しても、目の前の人に結局 ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」課題の分離1(7)
今回は、アドラー心理学のメインテーマとも言える課題の分離について取り上げます。
課題の分離はとても重要な箇所で、これが本当に実践レベルでできるようになると、ほとんどの悩みは吹き飛んでしまいます。このテーマは、複数回に分けて、紹介していきます。
課題の分離とは何か?課題の分離とは、課題が誰に所属するのかを明らかにして、他人の課題を自分の課題として悩み苦しむことから自分を解放することです。
アドラーは、「これは誰の課題のなのか?」と問いかけて、複雑に絡まった人間関係の問題を紐解いていこうとしました。
「これは誰の課題なのか?」と言われても、ピンとこないかもしれないので、「誰がこの行動を選択できるのか?」「最終決定権は誰が持っているのか?」ということで考えてみます。
例えば、夫がお酒を飲むことにイライラしている妻がいたとします。その時に、「お酒を飲むことは誰が選択できるか?」をまず考えます。
妻がどれだけガミガミ言おうが、嫌味を言おうが、夫は手段さえあれば、いつでもお酒を飲むことができます。24時間監禁状態でもしな ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」承認欲求(6)
今回は、承認欲求について取り上げます。
承認欲求とは?承認欲求というのは、「認められたい欲求」です。人は多かれ少なかれ、この欲求を持っています。仕事しているなら、「いい仕事しているね、助かるよ!」と言われるとやる気が出てきたり、勉強しているなら、「テストでいい点を取ってすごいね、本当に優秀だね!」と言われると嬉しくなったりします。
「君は本当に仕事ができないな!」とか、「本当に頭が悪いな!」と言われるのは、決して嬉しくはありません。
褒められて嬉しくなるのも、ダメ出しされて、がっかりするのも、自然な反応です。この反応そのものには、何にも問題ありません。
承認欲求とは、「認められたい!」という気持ちが『先』にあって、仕事を頑張ったり、勉強を一生懸命したりすることです。
人間誰しも、承認欲求はありますが、この欲求の比重が高くなってしまうと、自分の夢に向かって挑戦したいとか、こういう勉強をしたいとか、自分の成長や楽しさから、物事に取り組むよりも、「人から認められる」ということを目的に努力してしまいます。自分の人生なのに、他人の ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」劣等感(5)
今回は、劣等感について取り上げます。
前回このシリーズで、「自分が嫌い」な人について書きましたが、「自分が嫌い」も、劣等感を感じているからこそ出てくる気持ちです。
劣等感の言葉の意味劣等感という言葉は、そもそもどういう意味なのか考えた事はありますか。
アドラーはドイツ語の「劣等感」という意味を「劣等感」=「価値」+「より少ない」+「感覚」に分解しています。「~ができない」とか、「人から下位に見られた」「人より優れていない」など、劣等感の感じ方は様々ですが、共通しているのは、確かにいずれも自分の価値が下がったような気持ちになるということです。
無力感を感じたり、自信喪失して自分のことが嫌いになったりすると、自分の価値を正しく認識することが難しくなってきます。
ただ、確認したいのが、そもそも価値というものは、人がどう定義するかでどんな風にも変わってしまうものです。何も決められた「価値」というものがあるわけではありません。これは事実であり、とっても大切な考えです。
「みんな違って、みんないい」金子みすずの「わたしと ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」自分が嫌い(4)
今回は、「自分が嫌い」というテーマを取り上げます。
自分が嫌いのまま「幸せ」になることは難しいです。人生が充実している人、何かに挑戦して努力している人、他人に尽くしたり親切ができる人は、「自分」に対して、肯定的であり、その「自分」がやっていることも受け入れています。
自分が「自分」であることを「良し」とし、自分を大切にします。
【やる気がない時のすすめ】自分を責めずに、やる気のない自分を受け入れて!
【自責癖をなおしたい!】自分を責めてしまう癖があるときの対処法
長年、何かに悩み続けていたり、うつ病や依存症に苦しんでいたり、対人関係を極端に避けようとする人は、自分を肯定的にはなかなか受け入れません。
落ち込んでいる自分に対する、そんな中で世間の風当たりや他人の冷たさを感じたりしたら、自分に対する自信をますます失ってしまいます。
アドラーの「目的論」に当てはめるアドラー心理学は、目的論でも書いた通り、「~だから~」のロジックは否定します。
だから、「自分が嫌い」だから、人と接することができな ...
アドラー心理学「嫌われる勇気」変化(3)
今回は、変化について取り上げます。
アドラー心理学「嫌われる勇気」のシリーズ3回目です。
1回目:アドラー心理学「嫌われる勇気」目的論(1)
2回目:アドラー心理学「嫌われる勇気」選択(2)
人は心の隅では変化を求めています。でも、思うように変わりきれない自分に失望して、変わろうとすることをやめたり、言い訳したり、先延ばしにしたりします。
それでも「変わりたい」という思いが完全に消えて無くなるわけじゃありません。常に頭の片隅に残っているんです。
「嫌われる勇気」(岸見一郎著、ダイヤモンド社)では、こういう状況を「苦しい生き方」(P56)と言っています。
変化することをやめた時に、同時に「変化したい」という欲求も消えて無くなるなら、もっとシンプルかもしれません。
でも、人間は常に向上したいし、幸せになりたいし、そもそも「嫌な」状態を避け、「良い」状態を求めるのは、人間の根源的な欲求です。
「やりたくてもやれない」、「分かっているけれどできない」、「やった ...