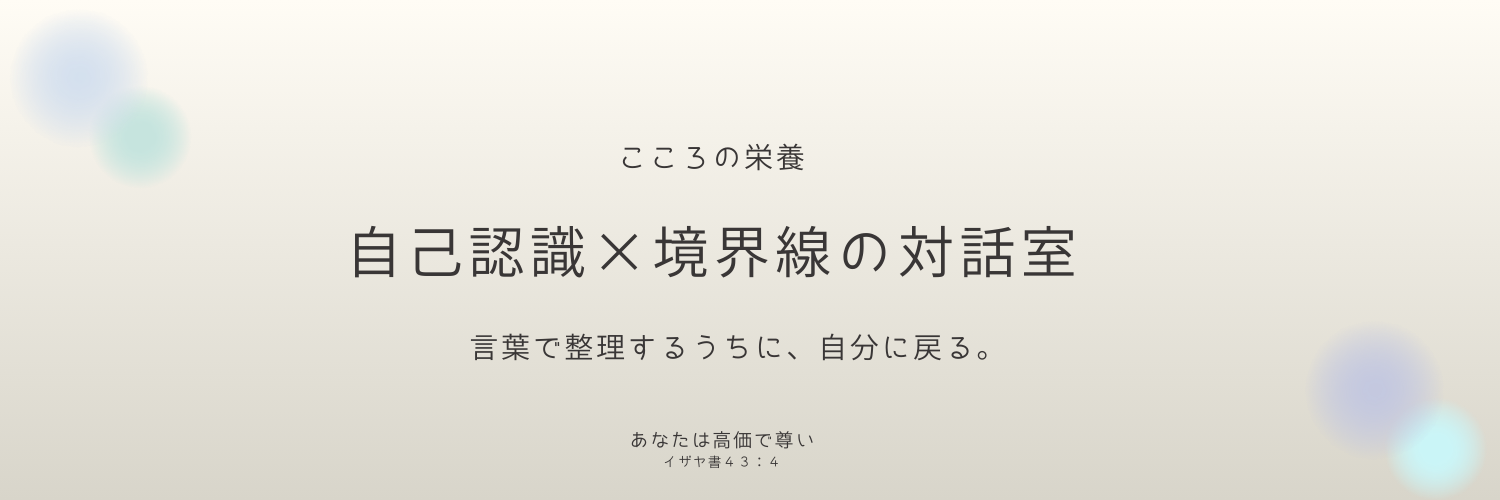他人に振り回される人生をやめる:自分の境界線を知って心が楽になる方法
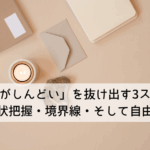
✔︎ 相手の問題を本当に把握しているのか?
✔︎ 自分の課題は何か?
✔︎ 自分に見えていないことがあるとしたら、それは何か?
✔︎ 気づいていても、なぜ実行できないのか?
✔︎ 何を恐れているのか?
✔︎ 何に満たされていないのか?
✔︎ 何にイライラしていて、何が不満なのか?
✔︎ 結局のところ、自分はどうしたいのか?
✔︎ どこまで理解していて、何が分かっていないのか?
理解していることに対して、自分に何ができるのか?
苦しみ、絶望、悩みで心がいっぱいになると、人は混乱状態に陥ります。
鏡に映る自分の姿は一見冷静でも、内面は荒れ狂う嵐のよう。
そんなときは、「変えよう」とせず、現状を把握することが第一歩です。
変化を求める必要はありませんもがいて何と ...
「どうしてこうなった?」ばかり考えて、疲れてない?
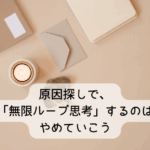
原因探しで、疲れていませんか?
たとえば、
「私って、なんでこんなふうにできないんだろう?」
「どうして、いつもこう考えてしまうんだろう?」
…そんなふうに、自分を責めること。
これって実は“期待”があるからなんです。
こうできるべき。
こう考えるべき。
そんな「自分に対する期待」を、無意識に持っています。
そして、自分でその期待をつくっておきながら、
自分で応えられずに、苦しんでしまうんです。
じゃあ、どうしたらいいのか?
「その期待、とんかちで叩いて壊しちゃいましょう。」
…なんて言うと、ちょっと極端に聞こえるかもしれませんね。
でも、本当に大事な問いはこれです。
「思い悩む原因になっている“期待”って、本当に持つ価値があるの?」
とはいえ、なかなか手放せない。なぜかというと、
「今は無理だけど、いつかは期待に応えられ ...
過去を受け入れるとラクになる。他人の目に振り回されない境界線の持ち方
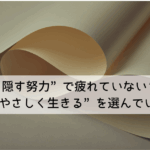
私たちは、ときどき過去の自分を隠したくなります。
「あんな失敗、誰にも知られたくない」
「こんな自分、見られたらどう思われるんだろう?」
そんな気持ちがあるのは自然なこと。
でも、それを隠すために気を張っていると、心がどんどん疲れていきます。
その労力は、本来の自分ではなく「他人の目」に向けて使っているから。
そして、誰かの目を気にして“見られたくない自分”を隠す努力って、
実は自分に優しくないんです。
そもそも、「他人がどう思うか」は完全に他人の領域。
そこに踏み込みすぎると、心がすり減ってしまいます。
境界線を持つことは、「人と距離を置くこと」ではありません。
それは、自分の心の体力を守るためのもの。
たとえば、こんなふうに問いかけてみてください。
「これは相手の問題。私は私をどう扱いたい?」
そうやって、自分の内側に意識を戻していくことで、
少しずつ“他人軸”から“自分軸” ...
質問をスルーされた、仲間はずれ…そんなとき、自分をどう守る?
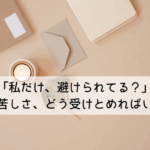
想いの箱に頂いたメッセージを紹介します。
こんにちは。
私は、ある教室に通っている(1クラス7人程度)のですが、単刀直入に私だけ、講師に除け者にされています。指されませんし、質問はスルーです。道は妨害されます。
初めの頃はそんなことはなかったのですが、段々とそのような傾向が見えてきました。
先日、思いきって、この講師に質問をしました。「私を避けてらっしゃいますか?」と。
そうすると、「いいえ、そんなことありませんよ」と返されました。
一瞬、自分が被害妄想かと疑いもしたのですが、明らかすぎて・・・
判断材料は少ないですが、このケース、背景にどんなことが隠されていて、また、どんな解決策があるのかその辺りご指導頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
ちなみに、今の段階だと私は教室を辞めようと思っています。
こんにちは。
再度ご連絡くださり、ありがとうございます。
「私だけ講師に除け者にされている ...
怒りの裏にある“期待”とどう向き合うか──人間関係が整う丁寧なコミュニケーションの始め方
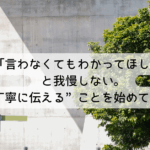
今回は、「怒りとの向き合い方」についてお話ししたいと思います。
怒りの奥にある「期待」とどう向き合うか怒りの感情の背景には、実は“期待”が隠れていることがよくあります。
私たちは無意識に、「相手にはこうしてほしい」「こうあるべきだ」と期待しています。
そして、その期待が裏切られると、失望や悲しみを感じ、それが怒りへと変わるのです。
では、「期待しなければ怒らずに済むのでは?」と思うかもしれません。
確かに、期待を手放せれば、他人の言動に過剰に反応せずにいられる場面は増えるでしょう。
ですが、私たちは人間。
親、パートナー、上司、友人に対して「こうであってほしい」と願うのは自然なこと。
期待そのものが悪いわけではありません。
大切なのは、「どんな期待をしているのか」を自覚すること。
そして、その期待を自分の内側に押し込めるのではなく、
「丁寧なコミュニケーション」によって、相手に伝えていくことが大事なのです。
相手に思いを伝えるには、 ...
「満たされている?」― イライラ解消の魔法の質問
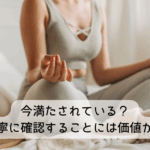
「なんだか今日もずっとイライラしていた」――そんな日、ありませんか?
実はイライラは悪いことではなく、体と心からの大切なサインです。
トイレを我慢している時や、お腹が空いているとき。
そういうちょっとした不快感が重なると、人は自然とイライラします。
これが一瞬なら自然なこと。
でもそれが何時間も、何日も続いてしまうと、人生そのものが「イライラを我慢すること」で埋まってしまうのです。
そんな状態を放っておくと、無意識のうちに疲れがたまり、余裕がなくなって、心までカサカサに。
まずは「今、自分は満たされているかな?」と問いかけてみることから始めてみましょう。
イライラを手放す第一歩は、自分に問いかけることです。
その質問は、とてもシンプル。
「今、自分は満たされてる?」
この問いを自分に向けてみると、驚くほど本当のニーズに気づけます。
たとえば、実は喉が乾いていた、お腹が空いていた、眠れていなかった―― ...
【想いの箱】大切な人から連絡がない…心がざわつく時の向き合い方
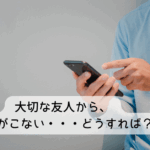
想いの箱に頂いたメッセージに回答します。
いつも、拝読させていただいています。
ご相談です。
もう何年と付き合いのある友人とパッタリ連絡が取れなくなってしまいました。
メールをしても一方通行で、返信がありません。
あまりしつこくしてもよくないと、今は様子を見ていますが、とても気になっています。
相手のことなので、わかりませんが、こちらに原因があるなら改善したいのですが、もし、友人や、その家族が病気だったらとかも考えてしまいます。
いずれにしても、今は連絡を待つしかないでしょうか。
とても、大切な友人です。
こんにちは。
メッセージをありがとうございます。
ご友人にメールをしても返信が来ないということで、
不安やそわそわした気持ちになるのは、とても自然なことです。
突然連絡が途絶えると、「何かあったのではないか?」と心配になるのも当然です。
特に、長年関わってきた大切な友人であればなおさら、その気持ちは無理もありません。
ですが、今の段階であら ...
【想いの箱】挨拶しても返されない…そのとき心に起きていることとは?
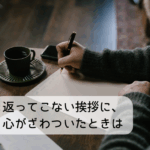
今回は、想いの箱に頂いたメッセージに回答します。
こんにちは
職場の上司に、モヤモヤしています
挨拶をしても、殆ど返ってきません
他のメンバーには、感じの良い対応をしている様に感じます
これも、境界線が曖昧で起こっているのでしょうか?
挨拶は基本だと、私も相手をジャッジしているのでしょうか?
こんにちは。メッセージありがとうございます。
職場の上司に対してモヤモヤを感じているとのこと、
特に、「挨拶をしてもほとんど返ってこない」というのは、
寂しく感じて当然だと思います。
無視されたり、スルーされたりすると、心がザワザワしてしまいますよね。
さらに、他のメンバーには感じの良い対応をしているとなると、
「どうして自分だけ?」という気持ちになるのも自然なこと。
疎外感、孤独感を感じてしまって当然です。
ここで一度、起きている出来事を整理してみましょう。 ...
「境界線を持ち始めたら、人が離れていった…」そんな寂しさとどう向き合う?

「もう我慢するのはやめよう」
「自分を大切にしよう」
そう思って、少しずつ人との距離感を見直し始めたとき。
ふと気づくと、関わる人が減っていた。
以前は毎日やり取りしていた人と、ぱったり連絡がなくなった。
誘われることも、頼られることも減ってきた――。
そんな状況に寂しさを感じて、
「これって間違っていたのかな?」と不安になることがあるかもしれません。
でも、それは「失敗」でも「間違い」でもありません。
ただ、あなたの生き方が、少し変わり始めているだけです。
「境界線を持つ」と聞くと、極端に受け取ってしまう人もいます。
たとえば…
距離を置くなら一切関わらない
自分を守るには、人を遠ざけるしかない
こうした考え方は、一見「自己防衛」のように見えて、実は白黒思考です。
付き合う or 付き合わない。ゼロか百か。全部か、全部ナシか。
でも、現実の人間関係ってそんなに単純じゃありませ ...
「いい人」をやめたい。そう思ったときに考えてほしいこと
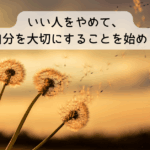
そう思ったときに考えてほしいことについて取り上げます。 「なんか最近、しんどい」 「人と関わるのが疲れる」 「どうして自分ばかり、我慢しているんだろう」 そんな気持ちがふくらんできたとき、心のどこかでこう思うかもしれません。 「もう、いい人でいるのはやめたい」と。 でも実際には、簡単に“やめられない”のが現実だったりします。 なぜなら、「いい人」であることが、
あなたの人間関係や生き方に、長いあいだ深く根を張ってきたから。 今回は、「いい人をやめたい」と感じたあなたが、
何をどう考えていけばいいのかを整理してみます。 そもそも「いい人」って、どんな人? 「いい人」は、一見とても聞こえが良い言葉です。 優しくて、親切で、気がきいて、周りを大切にできる人。 でも、ここで言う“いい人”は、ちょっと違います。 – 本当は嫌だけど、相手を傷つけたくなくて断れない – 頼まれると「NO」が言えず、いつも自分が後回し – 空気を読みすぎて、いつも疲れている – 自分の気持ちは、相手次第で ...